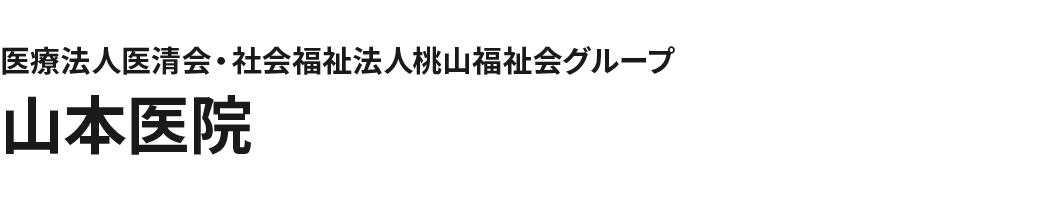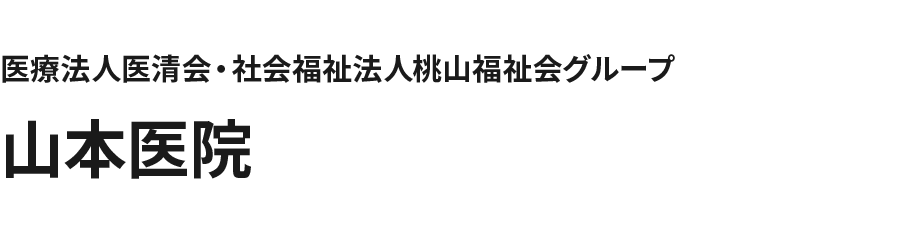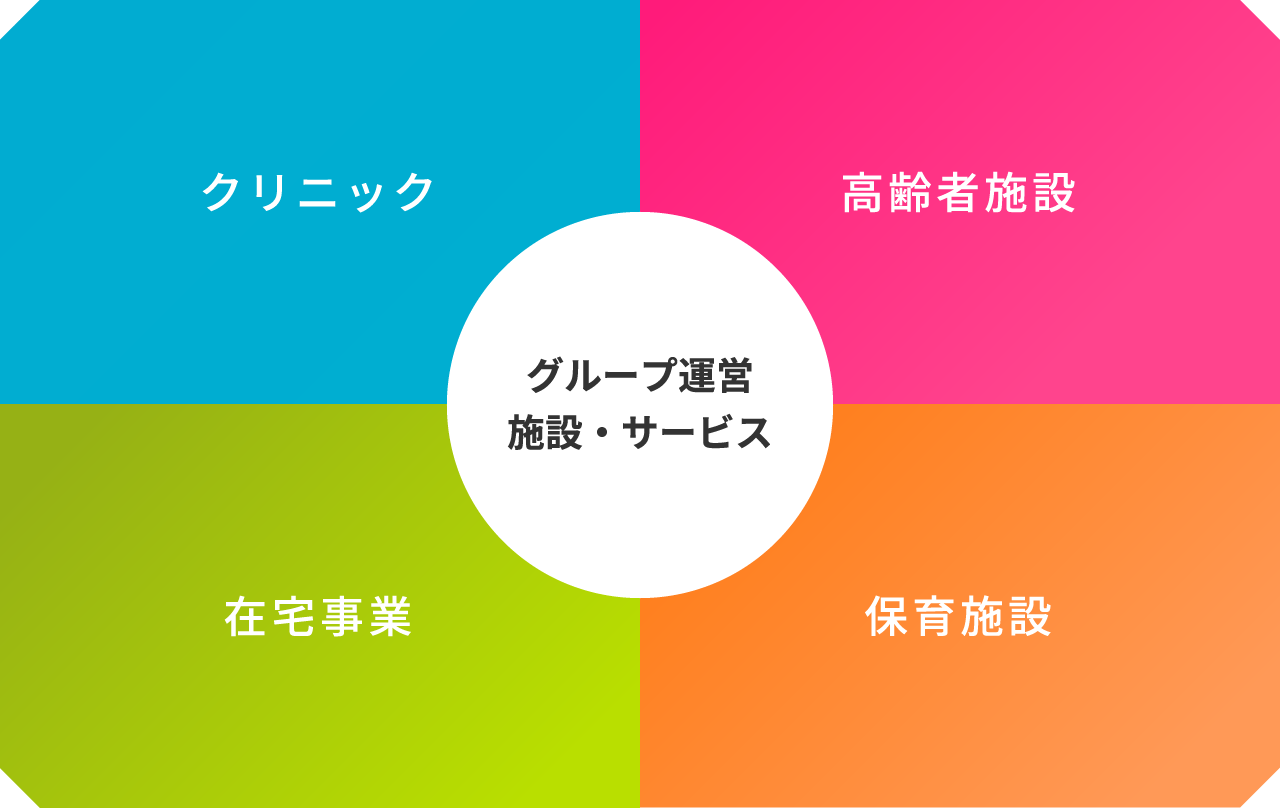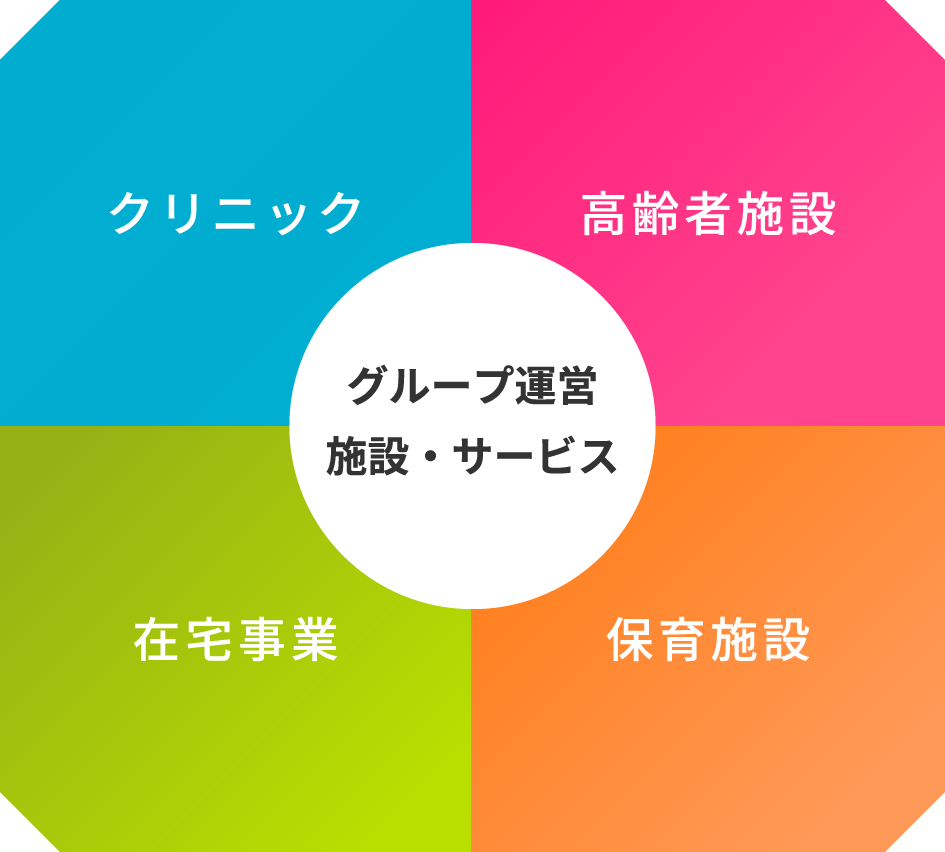のどの渇き・尿の量が多い
のどの渇きや尿量が気になる方へ
「水をたくさん飲んでものどが渇く」「トイレの回数や尿の量が増えた」「夜中にも何度もトイレに起きる」
こうした症状は、体の水分バランスやホルモンの異常が関係していることがあり、特に糖尿病や内分泌疾患の初期サインであることもあります。
気になる変化があれば、早めの受診をおすすめします。
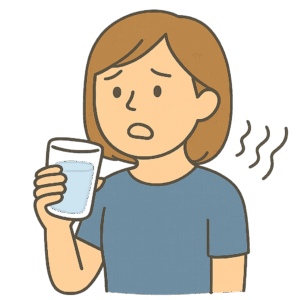
のどの渇き・尿量増加から考えられる主な病気
糖尿病
- 血糖値が高い状態が続くと、尿の中に糖が出て水分と一緒に排出されるため、脱水症状や口の渇きが起こります。
- 尿量の増加とともに、疲れやすさ、体重減少、感染症へのかかりやすさも見られることがあります。
尿崩症(中枢性・腎性)
- 抗利尿ホルモン(ADH)の分泌異常や、腎臓の反応低下によって、尿を濃縮できず大量の尿が出ます。
- 水をたくさん飲んでも渇きが治まらず、1日に数リットルの尿が出ることもあります。
心因性多飲症
- ストレスや心理的要因から、過剰に水を飲んでしまう状態。
- 水分過多により尿量が増えますが、ホルモン異常は認められません。
利尿剤などの影響
- 高血圧や心不全の治療薬として使われる利尿剤により、尿量が増えることがあります。
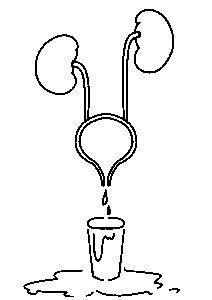
当院で行う検査・診察の流れ
のどの渇きや尿量増加の原因を探るため、以下のような診察・検査を行います。
- 医師による問診と診察(水分摂取量、尿量、体重変化など)
- 血液検査(血糖値、HbA1c、電解質、腎機能、ホルモン関連)
- 尿検査(糖・タンパク・比重など)
- 必要に応じて内分泌専門医の紹介
当院での治療とサポート
原因に応じて、次のような対応を行います。
- 糖尿病:食事指導、運動療法、薬物療法を組み合わせて治療
- 尿崩症が疑われる場合は、ホルモン検査や内分泌専門医と連携
- 心因性のケースでは、精神的サポートを含めた対応
- 利尿剤の調整が必要な場合は、処方医と連携して見直し
早めの対応が健康管理につながります
「水を飲んでも渇きが治まらない」「尿の量が多くて夜も眠れない」
こうした症状を放置せず、まずはご相談ください。
山本医院では、糖尿病をはじめとする代謝・内分泌の不調を早期に発見し、患者さんに合わせた丁寧な治療を行っています。
参考文献・出典
- 日本糖尿病学会『糖尿病診療ガイドライン2023』
- 日本内分泌学会『内分泌疾患診療ガイドライン』
- 厚生労働省 e-ヘルスネット

執筆者 山本医院(岡山市)副院長
山本 修平(やまもと しゅうへい)
大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)卒業。東邦大学医療センター大橋病院、国立病院機構東京病院、厚生中央病院、都立駒込病院、神戸百年記念病院などで消化器疾患全般の診療経験を積む。
- 〈専門分野〉一般内科、消化器内科、内視鏡診療(胃カメラ・大腸カメラ)、肝臓病
- 〈保有資格〉日本内科学会 認定内科医、日本消化器病学会 専門医、日本消化器内視鏡学会 専門医